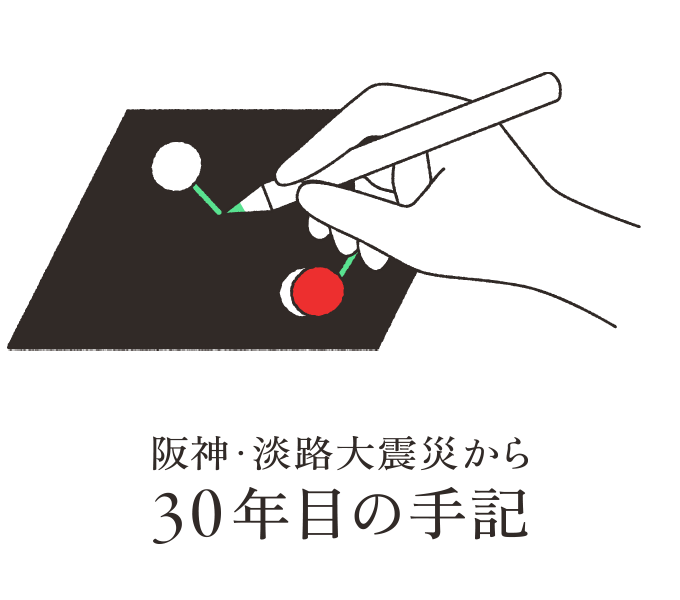まるでレンズを絞るように核心部分は鮮明に浮かび上がり、輪郭は遠く霞んで見える。1.17を迎えるたび、自動再生される回想シーンは毎年変わらない。大地の突き上げに四つん這いで踏ん張ったこと、定位置を失った家具を掻き分け子供部屋の扉を蹴破ったこと、夜明け前の仄暗い空と埃っぽい匂い、耳を擘くような悲鳴。
想像も予見も及ばない喪心の一日は、反芻するたびに記憶を上書きしどんどん色濃くなっていく。直接見聞きした物事は30年経ってもすぐ傍にあるのに、伝え聞いた話や自分の発した言葉は色褪せやがて消えていく。感じたこと伝えるべきことを文字や音声にして残す本当の意味を知るのは、ずっと後になってからだった。
10月の終わりに岡山の中学生から震災に関する取材を受けた。誰かにこれほど詳らかに話したのは何年振りだろう。まるで昨日のことという比喩が1.17の常套句のように、頭にこびり付いて離れない映像を言葉に乗せて吐き出した。
一通り当時を振り返った後、彼が住む街の周辺環境を聞いてみた。内陸部で海岸からは少し距離があるようだ。地域の特徴や過去の災害を踏まえると、神戸とは異なる対策が浮かび上がる。この一帯では南海トラフよりも河川の氾濫に注視すべきではないかと、心構えや準備すべきものについて共に思いを巡らせた。過去を振り返るだけでなく、常に情報と自分自身をアップデートすることの重要性を改めて認識し、次世代の純粋でストレートな問いかけに心が動いた。
「世」という漢字の成り立ちは、十を三つ合わせたもので「三十年」を表しているそうだ。同時にそれは一つの世代の長さでもある。親から子へ神戸の史実を伝える時、震災は避けて通れない出来事だ。世代間の語り継ぎが行われた結果、親世代が体験した未曾有の災害を自分事として捉えられる年代に達し、まるで申し送りをするように次に続く世代が声を上げ始めた。広島や長崎がそうであったように、受け継ぎ残そうとする次世代の意志を神戸が育んでいる。
一方でボランティア精神もこの30年の間に根付いたものの一つだ。震災を記録したり、当時4歳の娘に震災の記憶を擦り込もうとしたり、いずれ薄れていく神戸の記憶を当時から憂えていたが、あの頃何も出来なかった虚無感と焦燥感は、30年経った今でも消えることはない。神戸に寄せられた熱いエールに少しでも応えたいと今でも思う。
東日本大震災ではボランティア仲間とチャリティTシャツを作り、能登半島地震ではチャリティフットサルを企画して寄付を募った。募金箱を差し出すだけではなく、慈善活動の敷居を可能な限り低くし、一人でも多くの人が前向きに活動できる後方支援の在り方を模索し続けた30年でもあった。
続けることに意味がある。続けてきたからこそ見える景色がある。継続という柔らかい事実そのものが、今の私を支えているのかも知れない。微力でも自分にしかできないことを探り続けていきたい。
タイトル
引き継がれたバトン
投稿者
山中隆太
年齢
65歳
1995年の居住地
神戸市東灘区
手記を書いた理由
肉親や友人の死に直面しても、あれほど生死の境目を如実に突き付けられたことはなかった。
時間は唐突に途切れるものであり、昨日の続きが今日ではないと思い知らされたあの日から、娘が見えなくなるまで見送ることを今なお止められずにいる。
前を見据えて続けていることもあれば、過去を引き摺り続けていることもあるが、長いようで短かった30年という区切り線の向こう側に見えたものを書き留めてみた。震災で生き残った者として、伝え続けなければならないという一種の義務感を抱えながら。