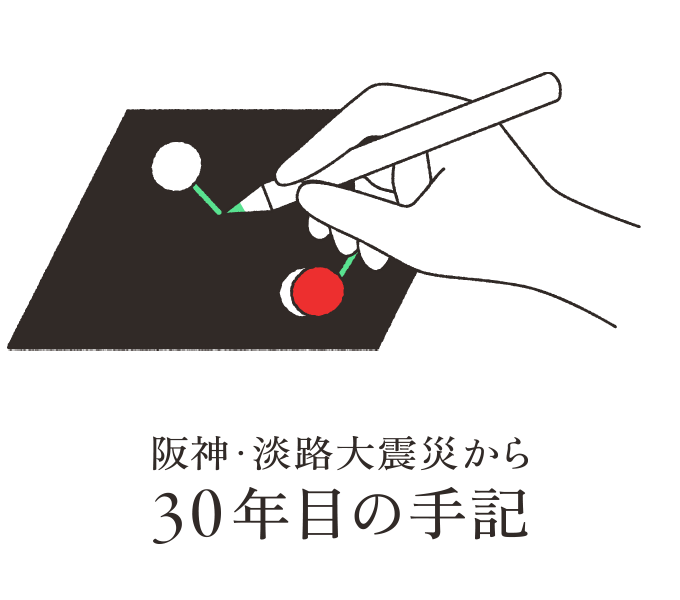「なんでママはトイレする時、いつもドア開けたままにするん?」
「ママなぁ、せまいところきらいやねん」
「トイレがこわいん? へんやなあ」
私がまだ小さかった頃、母とよくこんな会話をした。
阪神・淡路大震災から、30年。
いつの間にかきっちりと扉を閉めて用を済ませるようになった母は、どのような思いで30回目の「あの日」を迎えるのだろう。
私が生まれたのは、震災から3年後の冬だった。
2才になるまで親子3人で過ごした住吉川の近くの古いアパートは、復興公営住宅だったらしい。赤ん坊の私には、知る由もなかったのだけど。
2才になって弟が生まれ、三宮に引っ越してきた。
物心つくころには、震災を思わせるものは、町にはもうほとんど残っていなかった。
新しいビル、活気のある商店街、四季を彩る山並み、そして、どこへでも行けそうな気持ちにさせてくれる港。
幼い自分と震災との接点といえば、小学校のとき毎年歌った「しあわせ運べるように」と、いちご飴とベビーカステラを買ってもらえるルミナリエと、そして、折に触れて聞いた、母が語る「あの日」の話だった。
小さいころから、母はよく「あの日」のことを聞かせてくれた。
母の木造アパートが全壊したこと。
そのとき倒壊した建物の下敷きになり、寒空の下、救助を待ったこと。
そしてそのときから、狭い場所が苦手になったこと。
そんな話を聞かせてくれる時には、普段からはつらつとしている母の声が、いつもよりももっと、力強く聞こえた。
それでも、母が語る「あの日の神戸」、つまり、自分が生まれるたった3年前の神戸は、私が育った「神戸」からは遠く離れたどこかの町の話のように聞こえた。
「ママ、いつか行かなあかんと思ってるけど、まだ行かれへんなあ」
毎年1月17日に東遊園地で行われている、追悼式典のテレビ中継を見ながら身支度していた母が言う。
2020年1月17日。
いつの間にか私は、まだ短大生だった「あの日」の母の年齢を追い越していた。
「追悼式典、近いねんから行ったらええやん。ちょっと早起きしてさ」
母にそう言うと、予想外の答えが返ってきた。
「ママ、まだ心の整理ができてないねん。遠くで弔う事はできても、あの場所に行く勇気がないねん」
その言葉は、小さいころに「せまいところが嫌い」と言っていた母の声と重なった。
震災から25年経っていた。
全壊した母の家があった場所には、とっくに新しい建物が建ち、娘は成人し、トイレも扉を閉めて出来るようになった。
それでも、母の心の一部はずっと、崩れた木造アパートの中に閉じ込められているようだった。
「震災前の建物にそっくりやなぁ」
2021年4月。新しくなった阪急神戸三宮駅の、ピカピカの駅舎を見上げて、道行く誰かが言う。
崩れてしまった建物と、新しくできた建物。
神戸から去る人や、神戸に移り住んできた人。
30年の間にすっかり変わった神戸に、確かに存在し続ける面影。
誰かがそれを思い続ける限り、決して消えることはない。
タイトル
母の中の、あの日の神戸
投稿者
うみ
年齢
26歳
1995年の居住地
生まれていない
手記を書いた理由
私は阪神・淡路大震災を経験していません。
神戸の街で生まれ育った私にとって、阪神・淡路大震災は、自分の近くの人が経験した、でも、どこか遠くの町のお話のような、特別な存在でした。
これまでは、私にとって、阪神・淡路大震災は「両親や、身近な人が経験した大災害」でしたが、今回の企画を見て、たとえ経験していなくとも、自分の中に震災の記憶が刻まれているのだと気が付き、応募しました。