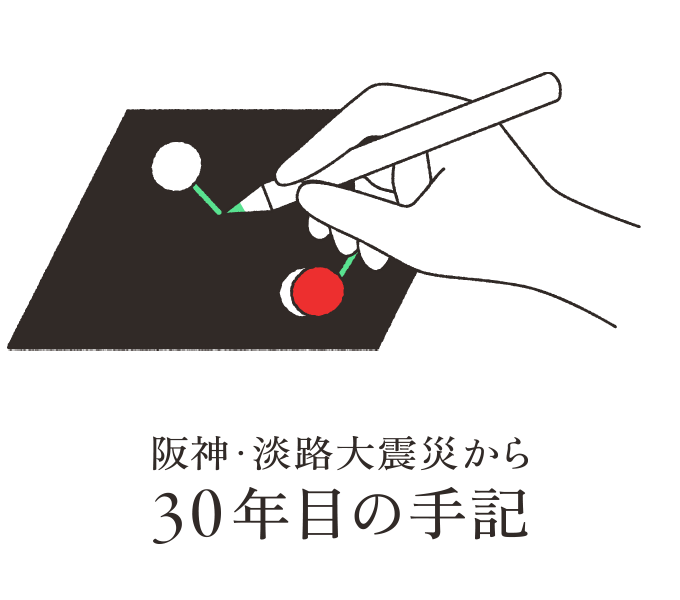私は、1995年の阪神・淡路大震災と2016年の熊本地震という、国内で数少ない震度7を2度経験した者の一人です。この経験をもとに、災害への備えと家族の絆の大切さを伝えるため、私の体験をここに記します。
阪神・淡路大震災発生当時、私は家族と共に生活していました。未明の激しい揺れの中、小さかった子どもたちを守るため、すぐに家族の部屋へ駆けつけ、倒れそうなタンスを支えながら子どもたちを安全な別室へ移動させました。幸い、自宅は倒壊せず、家族も無傷でした。その後、兄弟や両親と安否を確認し合いながら、家族の無事に感謝しました。
一方、熊本地震の際には、仕事の都合で熊本に単身赴任しており、地震発生から間もない状態でした。2016年4月14日の21時26分、前震と呼ばれる震度7の地震を、12階建てマンションの11階で一人経験しました。阪神・淡路大震災の自宅の2階とは異なり、高層階特有の揺れを感じました。情報源はラジオと携帯電話のみで、震度7と知ったとき、人生で2度目の強烈な揺れを実感しました。
翌日は益城町での調査のため現地に向かいました。熊本市内は目立った被害が少なかった一方、益城町では家屋の倒壊や道路の陥没を目の当たりにしました。しかし、阪神・淡路大震災で経験した被害規模と比べ、震度7の実態には違和感を覚えました。「これが震度7の被害か」という思いが拭えませんでした。
ところが、16日未明の1時25分、さらに大きな本震が発生しました。強烈な揺れで目を覚まし、机の下に潜り込みながら、間に合わない緊急地震速報を聞きました。一人暮らしの不安と恐怖が募る中、当時、東京、大阪、神戸、山口と各自離れた場所で生活している妻や子供達のメールがリアルタイムで送られ、恐怖感が薄らいだことを鮮明に記憶しています。この時のメールのやり取りは、家族や周囲とのつながりの記録として携帯電話の中に置いております。
災害の教訓を生かすことが大切であるとよく言われますが、阪神・淡路大震災の教訓は、私は建物の耐震性向上が命を守る最善の方法だと考えます。熊本地震では揺れているとき自宅のマンションは倒壊しないと確信できたこともあり、家族との安否確認がリアルタイムで出来たと思っています。ただ、当時は前震と本震の区分がされておらず、余震に対して油断していたことは事実でした。
南海トラフ地震が懸念される中、特に重要なのは、地震と共に津波を伴う複合災害の懸念があり事前の防災準備が生死を分ける鍵となるでしょう。その上で家族や個人は複数のどのようなタイムラインで行動すべきかを考え、事前に共有することです。津波や長周期地震動など、地域や状況によって異なる災害の特性に合わせた準備を継続的に行う必要があります。
私の震災経験を風化させることなく、次世代への防災意識向上に役立てたいと考えています。「怖い」という思いを一人で抱え込まず、思いを共有できる環境づくりが防災の第一歩です。
タイトル
阪神・淡路大震災と熊本地震--震度7を2度経験して
投稿者
辻本剛三
年齢
67歳
1995年の居住地
神戸市西区
手記を書いた理由
1995年の阪神・淡路大震災、2016年の熊本地震の体験しており、また、2011年の東日本大震災では、生まれて初めて津波警報を四国の佐多岬で聞いた経験がありますので、何か伝えることができればと思いました。