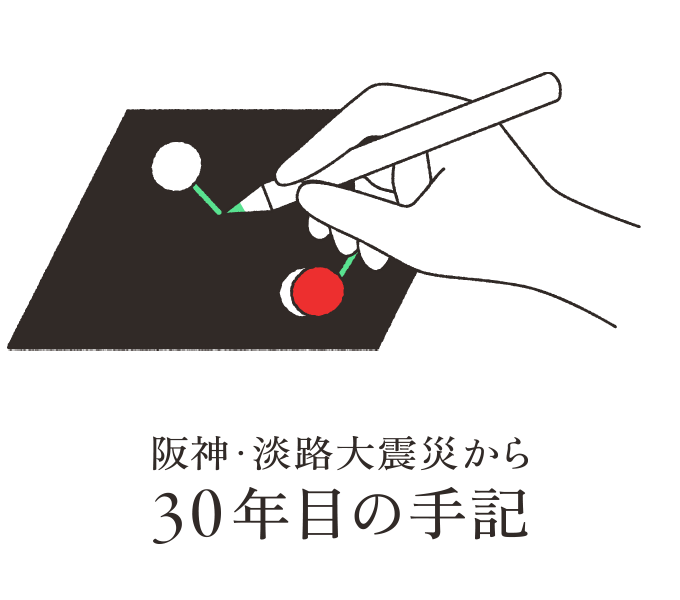18年前から、就職を機に神戸に住んでいる。その後、神戸のまちをあちらこちらと散歩するようになって、芦屋でも長田でも道端が広く整備されて電柱も地中に埋められた、綺麗な区画に遭遇すると、そこが震災後の再整備によって造られた街であることがわかるようになった。そういった景観以外にも、震災をきっかけに移転したお店、再建された建物、なくなった街並みなど、まちを歩くほどに地震による地層に気がつくようになる。
また、現実以外でも震災の地層がつくられているように思う。2010年にNHKドラマとして放映され、その後映画化された『その街のこども』(もう15年も前なことに驚く)では、佐藤江梨子と森山未來が神戸の街を歩き、話し、また歩き、話し、少しずつ解けていく2人の幼少期の震災の記憶が描かれていた。私がちょうど灘区に引っ越して来たばかりのタイミングでテレビ放映され、その後定期的に見返す度、2人の歩いた場所が自分にとって馴染みの場所になったことを感じる。
chapter22(高野雀)のZINEコミック『After the party』(2019)は、震災から数ヶ月後にクラブ(踊る方)が営業再開していると聞きつけた2人連れが三宮周辺を一晩ウロつく。作者の当時の記憶と資料から鮮やかに(そして少し猥雑に)ミドル平成のカルチャーが描かれていてナラティブな文化的資料としても価値があると思うのだけど、完売しており増刷の予定もなさそうなのが惜しい。
そして、『その街のこども』と『After the party』は、どちらも夜明けとともに話が終わるのだが、それぞれテレビドラマ/漫画の特性を活かした演出が美しい。
それから、木村紺の漫画『神戸在住』(1998〜2006)は本編の前日譚的に震災時の避難所のエピソードが挿入されており、希望や絶望、やりきれなさがジワっと胸に迫る。などなど、その他にも様々な震災に触れた小説、映像作品はその他の表現作品は多数あり(そしてまだ生まれていく)、当時のリアルな記憶が薄れていくことは避けられないが、神戸の文化に触れることは震災の地層に触れることになり、自分の中に入り込んでくるのだと思う。
タイトル
地層
投稿者
リトルレンズ
年齢
43歳
1995年の居住地
岐阜県岐阜市
手記を書いた理由
風文庫さんからのすすめで書いてみました。