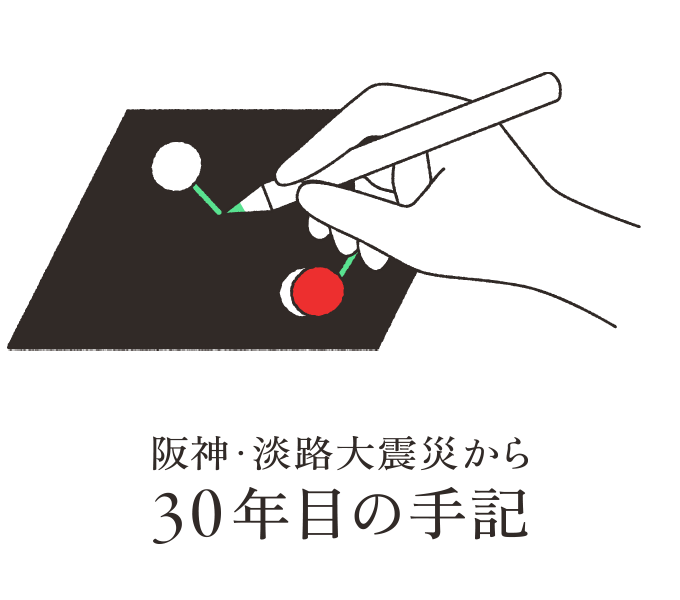私は阪神・淡路大震災当時、母のお腹にいて、その年に生まれた。
震災について初めて話を聞いたのは6歳の時。神戸で過ごした小学生までは、震災の話が学校でも家庭でも「当たり前」のことだった。また、実はこの震災で祖父母を亡くしていることから、直接会えなかったもどかしさを感じていた。
そんな私は、中学受験をしてたまたま少し遠い奈良の学校に通うことになった。ある日の授業で、震災に対する周りの大人たちの認識の違いを感じ、「ここは神戸ではないんだ」という実感が湧いた。それまで1人で遠くへ行ったことがなかったので、新鮮だった。
それから、小学校での防災教育や自分の生い立ちを振り返るようになった。そしてそれはこの学校に入ったからこそ得られた視点なので、何らかの形で活かしていきたいと強く思った。
しかし、いざ言語化しても、「実質経験していないでしょ」「まだお腹にいた時のことをわざわざ振り返るなんて」などと揶揄されることを恐れて言いづらくなってしまった。当時は、”震災を知っている世代が語り継ぐ”という風潮が強く、知らない世代が「受け身」になってしまうことも懸念した。
転機となったのは、震災から22年の時の番組で、自分の母と同じ、当時妊娠初期だった女性が取り上げられていたことだ。
私は改めて当時の厳しい状況を知るとともに、「ほんの豆粒ほどでも、命は命だ。当時の自分を取り巻く状況を知って、語ってもいいんだ」と背中を押されたような気がした。
今思い返すと、私のいろんな行動も、きっかけを辿れば「阪神・淡路大震災」に辿り着くことが多い。”震災”を巡って悩んだこともあったが、いろんな人たちと出会い、多くの経験ができたことは、もしかすると祖父母からの贈り物なのかもしれないと思うと感慨深い。
災害のような壮絶な出来事を前にすると、人はどうしても感情論に行きがちになる。上の世代は「生まれる前・小さい頃の出来事だから、どうせ何も知らないだろう」と、下の世代に対して諦めを持ってしまうことがある。しかしそうは言いながら、「下の世代に関心を持ってほしい」とも思っているという矛盾を抱えている。
もちろん、災害は経験した人でないと分からない部分は多いと思う。しかし、震災後に生まれた世代であっても、”家庭”という単位で見たら「震災と関係ない」とは限らず、想いを持っている人は意外と多いのではないだろうか。
震災から30年が近づき、いろんな世代や立場の方々が震災のことをいろんな角度から学んだり、調べたり、関連行事に参加したりするようになってきている。
その人だからこそ語れることがあり、語りの形は1つではない。私も引き続き、フラットに様々な出来事について語り、知ることができる場を大切にしていきたいと思う。
タイトル
震災と「語り」について
投稿者
福井莉緒
年齢
29歳
1995年の居住地
生まれていない
手記を書いた理由
震災から30年の間に世の中も変化してきた中で、自分自身も節目ごとに震災に対する向き合い方の変化があり、それを大切にしたいと思った。