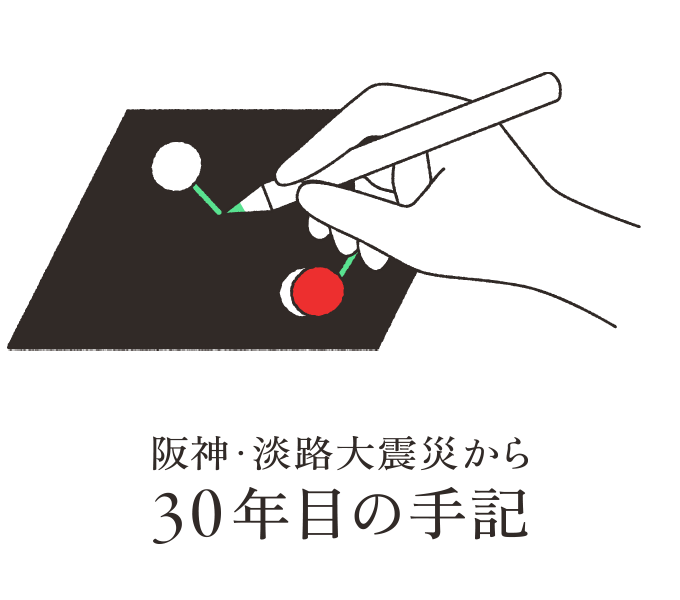あの日、自宅(団地の3階)で激しい揺れにより妻とともに突然起こされました。すぐに、また激しい揺れが襲い、小刻みにすべて体感可能な揺れがしばらく続きました。
しばらくの間、どうすることもできず、私の脳裏にはいつ2人で階段を降りて外に脱出するべきか、あるいは外に出たら上からガラスや物が直撃するのではと判断に苦慮していました。この間、足はがくがくするのみでただごとではない地震という認識はあるものの時間とともに身重の妻が腹痛を訴え、とにかく私にできることは何かと考えると、すまして食卓の椅子に座って新聞を読んでいる姿を妻に見せ続けることしかなかったと記憶しています。テレビでは炎と煙に包まれた壊滅した神戸の街が映されていました。
当日は、遅出の出勤で勤務先である障がい者施設に入らなければならなかったのですが、迫りくる地震の度に苦しみを訴えている妻、妻のお腹の中で怖がっている赤ちゃん、正直いって流産を覚悟していました。
一方、自分の仕事は社会福祉施設の介護職員である以上、何があっても出勤しなければならないと決断はしていても、夫、父である自分との葛藤はかなりあり苦しみました。
施設に着くと建物内部の亀裂のみで誰もけがもなく安心しながら、残してきた妻の身を案じながらその日の勤務は長い1日となりました。
余震が次の日もその次の日も続き、家庭と仕事との日々を何とかこなすのが精神的に精一杯なときに被災地の様子が明らかになるにつれ、自分がなにもしていないことに気がつき、何かしなければと焦る気持ちと連続勤務の中で私に出来たことは、献血でした。休みがやっときて1月20日に行った献血ルームでは既にたくさんの人々が来ており、私は献血ルームの中で5時間ひたすら待つことしかできなかったです。そして、私の順番がきて、私の血液が400ml採血されていく過程で私も含めここにいる人たちの血が少しでも命を救えるために役立って欲しいと瞼に涙を溜めて祈りながらベッドに横になっていました。
それから、2週間が経過し、その間、空は灰色、人々の心の中も同じような状態の中、神戸から勤務先の施設に緊急一時保護で重度の身体と知的の障がいのある方が陸上自衛隊のジープで8時間かけて搬送されてきました。避難所で、声をあげられるため、ご家族が周囲の方に気兼ねし、また充分な介護が出来ないとの理由でした。搬送してきた自衛隊員の方は、聞けば19歳の方が多く、疲れきっておられ、私たち職員が差し上げた熱いコーヒーをおいしそうに飲まれていた姿が印象に残っています。4ヶ月後、床ずれは完治し、その方はご家族の元に帰って行かれました。
結局、私や私たち施設の職員ができたことはそれだけでした。
タイトル
阪神・淡路大震災の日を忘れない
投稿者
山田洋一
年齢
64歳
1995年の居住地
大阪府富田林市
手記を書いた理由
あの日を思いだすたびに悲しみと後悔とそして行き場のない憤りに直面します。
今も、そしてこれからも「あの時、他にできること、他に助けることは出来なかったのか」と悔しさでいっぱいの気持ちがたまらなく溢れ出すことがあります。人の命はかけがえのないもの、そして、震災後に生まれた私のこどもや多くの人に、震災を語り継がなければならないと思っています。
と同時に、当時を知る人たちが一生懸命それぞれの役割を果たしたことを伝え、あの時に助け合った人の気持ちを考えることができる人に成長して欲しいと願っています。