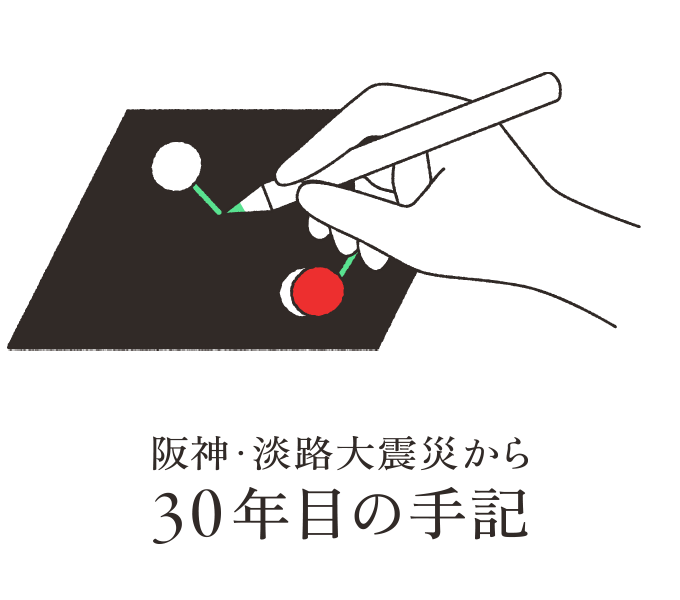あの日の夜は、満月だったと思う。蛙が車に轢かれたように押し潰された家々、1階や2階が圧縮され傾いたマンション、道路に散らばるブロック塀。夜になると何もかもすっぽりと暗幕がかけられたようだった。
少し濁った山吹色の大きな月は、その上に淡い光を放っている。月が雲に覆われると自分の手足すら見えなくなる。この世から光と音がすっかり消えてしまった。
地震直後出火した近所の家の炎は、更に勢いを増し、西から東へ延焼していく。夜になってようやく鎮火した。辺りにはガスの臭いと入り混じった焦げ臭い匂いが漂っていた。これは夢ではないか。明日の朝、日が昇れば、すっかり元通りになっているのではと、むなしい望みを抱いた。
あの日の早朝、地底からうめくような声がするやいなや、家が激しく上下に飛び跳ねた。訳がわからず、飛び起きると、今度は左右に揺すられ動けない。雨戸の向こう側では、何かが崩壊していくような轟音がする。猛烈な揺れはおさまることなく、永遠に続くように思われた。(このまま家は潰れたら、自分は下敷きになるんだろうか)生まれて初めて、死の恐怖をひしひしと感じた。
「おーい、おーい、大丈夫か。とにかく早く家から外に出るんだ」
隣室で寝ていた父の叫び声がした。
暗闇の中、ベッドから下りようとすると、足先に触れたのは、天井にぶら下がっていた電灯だった。その脇には、引き戸の扉が落ちていた。部屋を出るにも、廊下の本棚が倒れていて、扉がなかなか開かない。本をかきだし、やっとの思いで1階へ下りると、冷蔵庫の卵が、廊下に割れて散らばっている。応接間のピアノの角が壁にぶち当たり、穴を開けていた。外へ出ると、我が家は、倒壊した隣家が寄りかかり、半壊していた。JRの高架が落ちて、道路にVの字に突き刺さっていた。家もビルも倒壊して、はるか海の方まで見渡せた。そこかしこで、炎があがっている。母が、「戦時中の焼け野原を思い出す」と無表情に呟いた。
とにかくこの状況を職場や親類に連絡しなければならない。亀裂の入った道路沿いの公衆電話ボックスへ行くと、すでに20人ほどの行列ができていた。自分の番になったが、硬貨が一杯詰まっていて入らない。10円玉を必死に押し込もうとしていたら、後ろの人が、電話機をゆすってコインを中へ落としたらどうかと言う。私は、電話機を揺らして、なんとか10円玉を入れることができた。
夕方、倒れてきた家具の下敷きになり、頭から血を流していた父の具合が悪くなり、母が付き添って、1キロメートルほど離れた病院に行くことになった。流れていた頭の血が髪の毛を真っ赤に染めて固まっていた。洋服にも血痕が生々しく残っている。月夜の下、病院からいまだに戻らぬ両親を、私がいつまでも待っていた。
タイトル
あの日
投稿者
久留米愛沙美
年齢
64歳
1995年の居住地
神戸市東灘区
手記を書いた理由
東日本大震災で被災した知人に、お見舞いのメッセージと助力を申し出た時、真っ先に返ってきたのが、「ごめんなさい」という言葉で、意外で驚いた記憶がある。被災して初めて、阪神・淡路大震災でどれほど大変だったかがよくわかったという。「あの時、私達は何もしてあげられなくて申し訳なかった」というのだ。
あれから30年経った。最近では、全国の地方公共団体、図書館や博物館などで「デジタルアーカイブ」という言葉をよく耳にする。今回の企画を知り、一神戸市民として、被災者としての使命みたいなものを感じて、拙い手記を寄せる次第である。いつか震災を題材にした物語を書いてみたい。