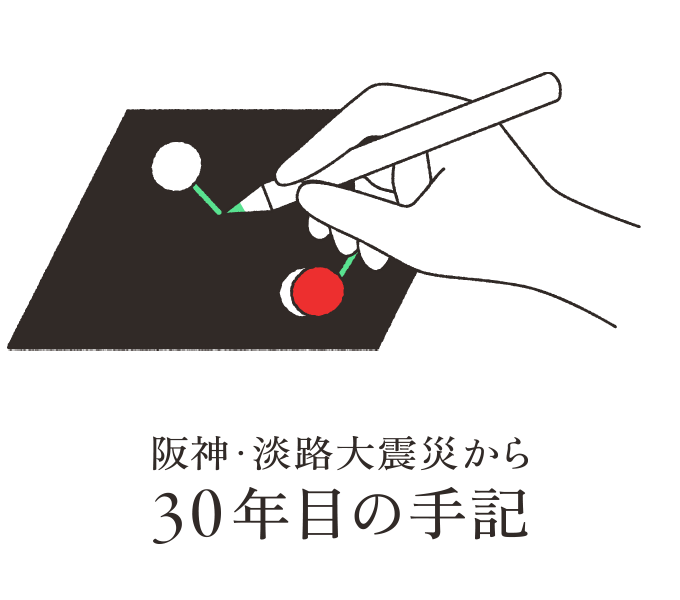1995年1月17日 連休明けの火曜日。年末に引っ越した東灘区の一人暮しの部屋で、当たり前の日常が始まるはずだった。暗いうちに目が覚めたと思った途端に大きな揺れ。本棚もテレビも吹っ飛んだが、枕もとの電話には手が届いた。早朝に電話をしても許されるのは父しかいないと実家に電話をして状況を聞く。この電話が家族への生存確認となった。
明るくなって窓から見える道の向こうの家々は壁が落ちて中の様子が丸見え。子どもの頃に遊んだリカちゃんハウスのように見えた。すぐ外で声をかけ合う人々の声、毛布を持ってきてという声が聞こえる。私は勤めていたフリースクールに通う一人暮らしの子どもの安否を電話で確認することになっていて、その中には行けない。それでも、私は自分のことしかしていないという罪悪感、焦燥感で落ち着かない。
安否確認が終わり、新しい冷凍庫付き冷蔵庫が嬉しくて前日に作った冷凍おむすびを持って自転車で青木から御影の職場に向かう。外に出た時の衝撃、戦後の焼野原の日本はこんなふうだったのだろうか。引っ越す際の候補の一つだった建物はあるべきところから見えなくなっていた。途中、1階が押しつぶされ2階で寝ていて助かったという友人に偶然出会う。どんなに怖かったことだろう。職場のみんなと合流し上司の家に向かう。時間感覚がなく暗くなるから夜になったと気づく。高台にある上司の家から見た神戸の街。真っ暗な中、いくつかの場所で大火災が起きているのが見えた。上司に「泣くな」と一喝される。
翌朝、フリースクールの一人暮しの子どもを大阪経由で実家に帰す引率をする。大きな家の立派な石塀が高級車の上に倒れている。形あるものは壊れる。アスファルトの道路が盛り上がり、亀裂から下の土が見える。こんなに分厚くコーティングされていたら地球もどんなに息苦しいだろう。法外な値段で靴やスリッパを売る店屋がある。その傍で何でも要るものを持って行ってと声をかける店主がいる。同じ状況に置かれたのに全く違う行動を選ぶ不思議。公衆電話の前に長い列。大勢の人が大変な目に遭っている中、私は無事で、知っている人もみな無事で、暖かい部屋で知った人たちと安心して過ごした。なぜ私は生きているのだろう。やるべきことがあるのだろう。では亡くなった人は役割が終わったのか、否、亡くなったことに意味がある。生き残った人がその死を活かす。そう思わないと崩れそうになる。阪急電車の線路の上をぞろぞろ歩く。普段ならわくわくする体験なのに、みんな下を向いて黙って歩く。西宮北口から電車に乗り梅田に着いた時の違和感。建物がまっすぐ立っている。道路が普通に機能している。いつも通りの時の流れ。それが当たり前かのように。
あの日のことを話そうとすると30年近く経っても理由のわからない涙が出ていた。この手記を書き、あの時の気づきを、私がまだ活かしていないという憤りと虚しさが理由だと気づくことができた。
タイトル
あの日の気づき
投稿者
太田望
年齢
60歳
1995年の居住地
神戸市東灘区
手記を書いた理由
芦屋市にある風文庫のオーナーさんと話す機会があり、阪神大震災の話をすると涙がぽろぽろ出るのはなぜだろうと問うと、一度手記を書いてみたらどうかと勧められました。