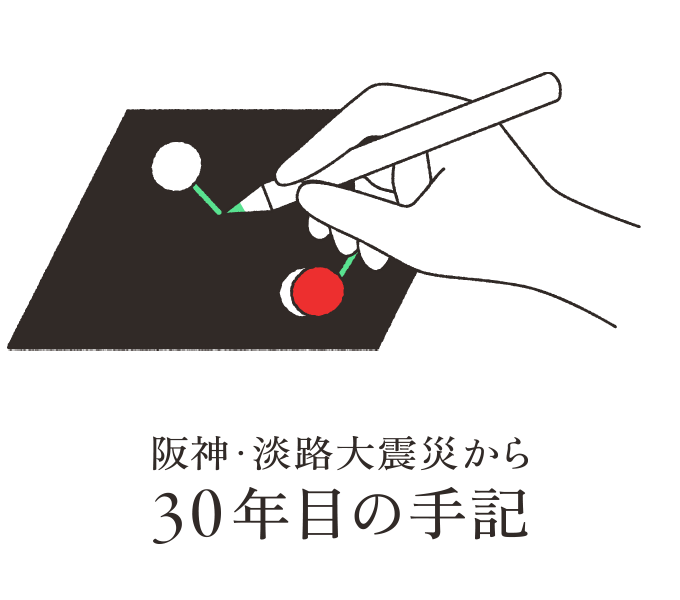当時、大阪の放送局で番組制作のデスクをしていた。我が家は全壊、家族にはけがはなく(母親、妻と小学校4年と2年の娘)翌日に阪急西宮北口まで歩いてたどり着き、そこから大阪城近くの職場に出勤。武庫川を越えた途端まったく風景が違って、梅田に降りたら、あまりに平穏、平然としていて明る過ぎてまぶしく、サンダル履きのままだったのでまず駅前の大丸で靴を買って……出社。
まがりなりに被災者であり、同時に取材者であるという複雑な、屈折した立場に置かれた。その時に感じたのは被災地の様々なことが、実情がどうして伝わらないのだろうというもどかしさ。
一番伝わらないのは「喪失感」ではなかったか。風景、住まい、生活、日常の喪失。自宅だけでなくお隣からずっと壊れてしまった家屋が広がる。平常の生活が奪われ、知り合いを失い、あるいは肉親すら失った方のいる、そういう光景は街の果てまで(芦屋から西側の東灘、森南町、本山と激震地区が続いて)続いていて……喪失の光景だった。
日々変わる被災地、被災状況。1995年1月17日は火曜日(敬老の日の振り替え休日が前日の月曜日)。水曜日に出社し、その日はいったん家族の避難先に戻る。木曜日は自宅の瓦礫を整理(というより衣服などを取り出すが、何から手をつけていいか分からない)。金曜日に再び出社し、そのまま土曜日朝の生放送に対応。番組は「被災地からの声」をテーマに「いま、何が必要か」とディレクターたちが総出で各地で話をきき、それを一斉にパターンに書いて張り出し専門家の先生に分析してもらう。
避難所での必要なもの、お困りごとの聞き取りだったと記憶しているが、その中に「道路が渡れない」というものがあった。阪神間は国道2号線、43号線(倒壊した高速の下道)それに3つの鉄路が東西に通っていて、信号が機能しないため通過する車が連なり、足の弱ったお年寄りにとっては川の様に南北の交通が分断されていた。浜側の親類宅に避難してそこから自宅の瓦礫整理に往復していた私にはその難儀さがすぐ分かったが大阪のスタジオにいる制作側はピンとこない。被災地の現状を曲りなりに知る私は、その旨を言って「信号を直してほしい」という希望の紙といっしょに掲載してもらった。ささいな事ではあるが、一事が万事であった。しかも被災地の状況は刻々と変わる。半日で変化する。取材して放送した時には、もう新たな課題が発生していた。
そしてひと月、ふた月、1年と経ていく。復興状況を報道する時、復旧・復興が進まず被災地にあまりに変化がなく、映像に変化がなくいわゆる「絵がない」状況が続く。そうなると番組になりにくいという。その時は「変化がないこと自体が問題なんだ!」と声を上げた。
その後の災害にあの時の経験は生かされていて今後も行かされる事を期待している。祈っている。災害は必ず来るのだから。
タイトル
個人的経験から――“被災者”であり取材者でもあった
投稿者
井上利丸
年齢
67歳
1995年の居住地
兵庫県芦屋市
手記を書いた理由
あの震災から30年が経ちました。その後、中越、能登、中越沖、東日本と地震・災害は続き、立場は違えど何らかの形で現場に関わることになりました。けれども、曲りなりに“被災者”という立場になって いわば取材対象の立場になったのは30年前の「あの日」の災害の時だけでした。
教訓めいたことを言いたい訳でなく、言えることもないのですが、いまも思っていて託せる個人的経験をつづりました。そして、被災地とその人々を忘れないでほしいと、それが復興の第一歩だという気持ちで。