
2024/8/24
イベントレポート
災厄の経験を分有する表現の可能性をさぐるリサーチプロジェクト「災間スタディーズ:震災30年目の“分有”をさぐる」。
7月13日(土)に、全3回にわたるゲストを迎えたケーススタディシリーズの初回となる第1回クロストークを開催しました。
第1回クロストークでは、アーカイブ・プロジェクトAHA![Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ] 世話人の松本篤さん、写真家の小原一真さんをゲストにお迎えし、高森順子さんを聞き手に、ゲストのこれまでの制作活動を振り返りながら、集合的な喪失体験の記録から表現をつくることや、それをいかに見るかについてお話いただきました。
まずはじめに、災間文化研究会の佐藤李青さん、高森順子さんよりプロジェクトやイベントシリーズに向けた思いをお話いただきました。佐藤さんからは、「災害と災害の間に生きている今、改めて私たちは災害にどうかかわっていくのか。このプロジェクトは出来事をどう伝えていくのかを考える場。大きな出来事と出会った人たちの体験は共有しえないが、出来事を伝える、それが「ある」ということ伝える方法として表現活動があるのではないか。このプロジェクトは、それらの言葉をキーワードに出来事をどう伝えていくのかを考えて行く場である。」と災間スタディースの活動の目的についてお話いただきました。続いて、高森さんからは、「何かに役立つために、こういう価値があるというものの手前、ただそこにあるという存在そのものに着目するのが分有の考え方。意味や価値や目的にたいするある種懐疑の眼差しを持ち、見えづらくなっているものに光を当てる活動を行う松本さん、小原さんの実践を神戸でお話することで、分有を考えることができれば。」と、今回のシリーズの企画意図についてお話をいただきました。

トーク前半では、ゲストのお2人から、これまでの活動についてお話を伺いました。
アーカイブ・プロジェクトAHA![Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ] 世話人の松本篤さんからは、「言葉の集め方/届け方」と題し、代表的な活動である8mmフィルムの保存活用プロジェクトを中心にAHA!の活動について、そして東日本大震災10年の際に企画された「わたしは思い出す」についてお話いただきました。
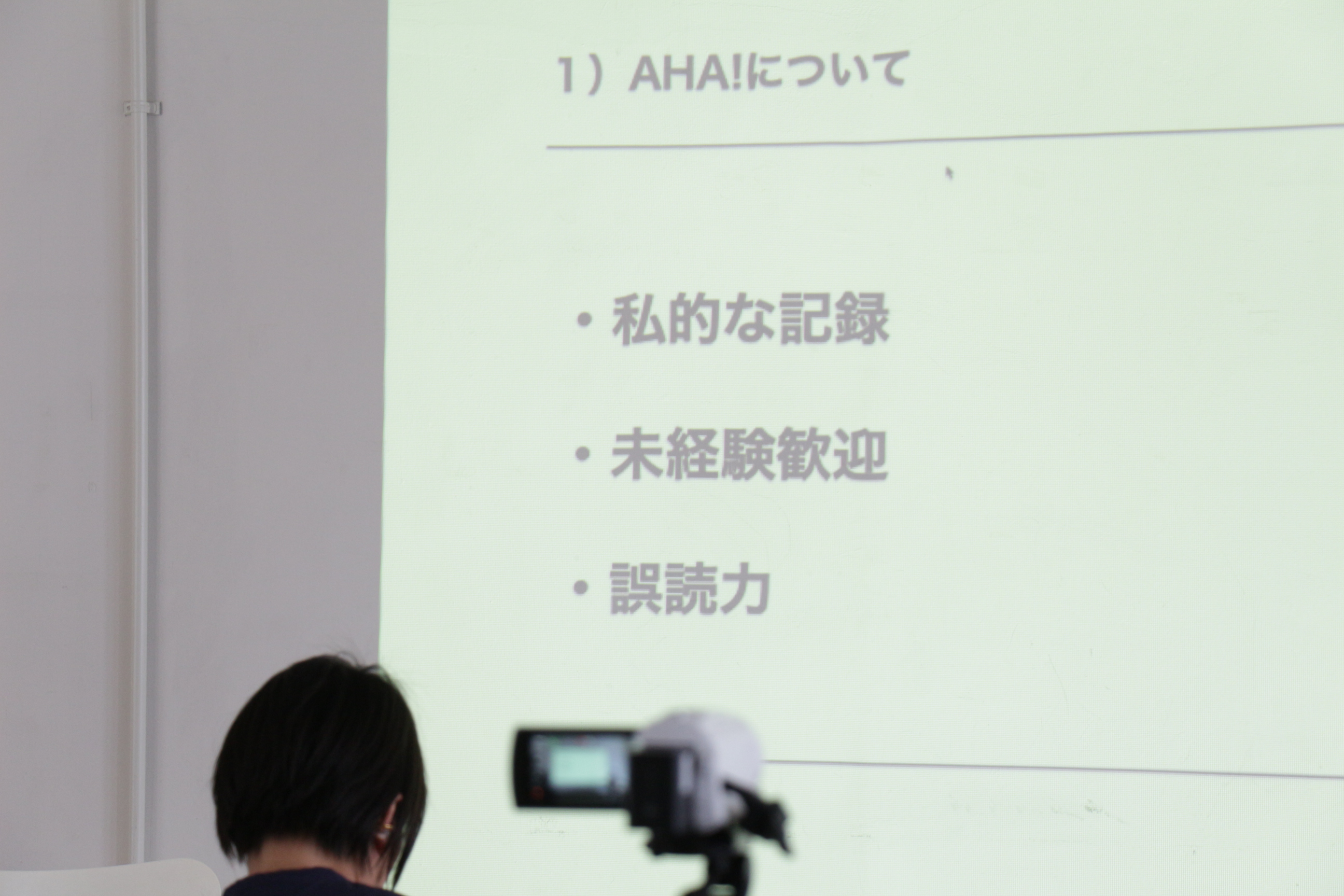
「8mmフィルムのアーカイブプロジェクトとして出発した時、私たちは3つのことをよく議論していました。1つ目が、著名人の残した資料だけでなく、市井の人々による記録をいかにアーカイブするのか。2つ目が、経験していないということを、どのように経験できるのか。3つ目が、記憶の継承を考える上で、誤読といった営みをいかに価値化できるのか。誰かの記録によって他の誰かの記憶が活性化するような、想起の波が伝播していく体験の場を〈生きたアーカイブ〉として提案したかったんです」と、AHA!としてのアーカイブの考えを提示いただき、続いて「わたしは思い出す 11年間の育児日記を再読して」の企画のプロセスと、その中でどのように記録と関わっていったのかをお話いただきました。仙台在住のかおりさん(仮名)が綴り続けた育児日記との出会いをきっかけに動き出したこのプロジェクトは、かおりさんの育児日記を、かおりさんが再読し、回想した言葉を松本さんが書き起こしていくという作業から生まれたものです。松本さんは、「固有の語れなさ、聞けなさがそこに存在していました。本や展示は、そこに読めなさを加える作業。三重の不可能性は、読者や鑑賞者によってはじめて継承の可能性として開かれる」といいます。日記の再読をきっかけに紡がれた回想の言葉から生まれたプロジェクトは、仙台市のせんだい3.11メモリアル交流館で展覧会を開催。その後、震災を経験した地である神戸にて巡回展が開催され、そして、30万字超の回想録として書籍として出版されました。松本さんは「展示会場にてアンケート『あなたの〈わたしは思い出す〉』を実施したんです(神戸篇・水戸篇)。来場者から届けられたそれらの言葉たちすべてに、継承の試みの実体が顕れていると思う」とお話されました。


続いて、写真家の小原一真さんよりお話をいただきました。はじめに「記録することの障壁、表現への認識の障壁をテーマに、表現がどのように乗り越える可能性を持っているのか。記録はどのようにあるべきなのかを考えたい。」という小原さんのこの場への思いをお話いただき、これまでの活動を紹介いただきました。

小原さんは、地震や津波、戦争などの災禍の真ん中にいるにも関わらず社会構造や差別構造の中で見えなくなっている人たちをどのように表現することが出来るかという考えのもとに活動をされています。はじめに手掛けたのは、福島第一原発で作業員として働く方たちのポートレートでした。写真家として活動するために海外移住を予定していた時に、東日本大震災が起こり、被災した友人を訪ね歩く中で、そこで福島第一原発で働く作業員の方と出会ったそうです。初めて知り合った作業員の方は、事故によって仕事を失ったけれども故郷を離れたくない。福島のために何かしたいけれども、周囲には仕事がない。そんな中、原発で働くことを決めたそうです。そこには加害者の元で被害者が働かざるを得ないという複雑な状況がありました。事故の最前線にいながらもメディアでその姿を見ることがない作業員との出会いから、26名の協力を得て、どのような思いで働いているのかをインタビューした写真集『Reset Beyond Fukushima』が作られました。その後も、社会の中で見えなくなっている人たちの話を聞きながら何らかの形で表現に出来ないのかという考えのもと、さまざまなテーマに向かいます。次は、事故の30年後を表現することを目的にウクライナのチェルノブイリに通いはじめたそうです。その後出版された写真集『Exposure』の中にある1枚のポートレートに写るモノクロームの美しい写真(以下写真のスライドを参照)。そこに写されているのは原発事故の4か月後に生まれマリアという女性です。マリアは、幼少の頃から精神疾患があると病院で診断されてきましたが、20歳の時にその原因は甲状腺の病気だったことがわかりました。事故当時、母胎内で被爆していたことを知り、チェルノブイリという存在が初めて自分自身と結びつきました。小原さんは、マリアという存在をどのように表現できるのかを考えていた時、チェルノブイリの汚染地域にある倉庫で見つかった、未使用の写真フィルムを譲ってもらいます。30年間誰にも気づかれずに汚染地域に置かれていたフィルムの存在がマリアと重なり、そのフィルムで撮影をすることがマリアという存在を、30年後のチェルノブイリを表現することになるのではないかと考え作品につながったのだそうです。


後半は、前半のプレゼンテーションを受けての高森さんからの質問にゲストのお2人が応答するかたちでクロストークを行いました。
高森:メディアは大衆をうつす鏡。お2人は忘れかけられているメディアを意識的に選んでいると感じます。そのようなメディアだからこその表現だと感じているのでしょうか。それは、想像の種としてか、制限や制約としてか、どちらと捉えているのでしょうか?
松本:小原さんもAHA!の活動も、歴史を以て歴史を壊していく、再構築していくという意識がありますね。例えば、写真を以て写真を壊していく。同じ機能、構造、メカニズムを使って全く違うものを再構築しようとされているように見えます。AHA!が8mmフィルムに着目する理由の1つは、8mmフィルムがひろく普及したタイミングが、批評や運動が活発だった「記録の時代」(鳥羽耕史)のあとから遅れてやってきたからです。記録の意味がどんどん変質していく時代の最先端に現れた8mmフィルムは、何を映し、何を映さなかったのか。スクリーンの外を想像するために8mmフィルムを再利用するという発想があります。
小原:解釈を再構築するとおっしゃられていましたが、「歴史の証言者」などとも言われるような戦争の写真記録は、その物語性を絶対的なものとし、同時に他の個人史などは見えずらくなっていきます。それを現代から読み直し、新たな表現とするときに、僕は、アウトプットとなるヴィジュアルは機械としての写真装置に出来るだけ委ねたいと考えています。自分のエゴをできるだけ遠くに置くための在り方として、カメラという機械装置を使っています。僕の手から離れたところで生み出されるものに一度委ねてみることで、自分の限界を超えたものができるのではないかと思っています。
松本:同じ「文房具」を使って、再生産のプロセスを再構築のプロセスに接続させようと試みている。なかなか簡単にはうまくはいきませんが、そこがチャレンジしがいのあるところです。
高森:機械装置に委ねたいというお話が出ていましたが、『はな子のいる風景』では、公募して集められたはな子と映った写真がキャプションとともにまとめられています。でも、そのキャプションはいわゆる写真の説明としてのキャプションではなく、はな子の飼育日誌がキャプションになっている。集められた写真は、象のはな子と家族が写っているけれど、はな子を見てはいないんですよね。動物園の構造から物理的な距離もある。小原さんの『Silent Histories』では、レプリカとして当時の印刷物が挟まれている。これも自分のコントロールを外していくということではないかと思いました。また、松本さんの「わたしは思い出す」では、「わたし」「わたくし」が沢山でてきます。この本では、再読作業を通してかおりさん本人ではなく「私」をつくりあげる協働作業をしていると感じました。作業を通して、松本さんでもない、かおりさんでもない「私」が立ちあがっている。当事者と関わることの匙加減といいますが、距離をどのように取っているのでしょうか?
小原:私の場合は被写体となる人が事前に決まっていることはほとんどなく、気になる場所を訪れ、偶然出会い、一緒にお酒を飲んだり、同じ時間を過ごす中で、その人に惹かれ、そういう人間関係の中で撮影するための具体的な問題意識が芽生え、撮影させてもらえないかと相談をすることが多いです。十分な予算で撮影に臨めることはほとんどなく、現地では色々本当に助けていただくことがほとんどで、泊まらせていただいたり、ご飯をご馳走になったり、ほとんど僕が迷惑をかけ続けるような状態で。裁判をしていたり社会問題に直面している人と関わる時に、記録者としての客観性みたいなものを考えた時もありましたが、まずは自分がその人と沢山時間を過ごす中で感じたことを大切にして、それが表現につながることが望ましいと考えています。惹かれたその人のことを、写真というメディアを通し、自分の手から離した時にどういうものが立ち上がってくるのか。
高森:偶然を誘発する可能性を呼び込むにも周到な準備が必要かと思います。そこから最後手をはなす、あきらめる。「わたしは思い出す」では、言葉を削り取る、演出するような要素もあるわけですが、つくられた本を読者にどう見てほしいというのはありますでしょうか。読者との関係をどのように考えているのでしょうか。
松本:複数のわたしの声を集めて受け手に届けたい。また、受け手自身にも未知なる受け手に言葉を運んでもらいたい。そのためには、なるべく偶発性を高めるというのが大事だと思っています。言い換えると、いろんなものを容れる丈夫なコンテナ、原稿用紙のマス目のような構造を、本や展示空間の中にたくさん作ること。それが編集やデザインという営為であり、私たちはそのスペースの中でなるべく小さくありたいと思っています。
高森:空間に例えれば、密度のある構造ではなく、どこからでも入れるようなもの。余地やユーモアを見せること。入口が多様であることが分有的に感じました。ただあるということを愛でることは、分有的な表現を考える上での一つの到達点のように思います。
小原:写真集って印刷する数も少ないし、値段も高いので手に取ってもらえる人が限定されます。その前提に立った時に、本の持つ価値を一番最初に考えます。例えば、大阪大空襲の本は裁判のために作った本なので、読者は裁判官でした。裁判官が、70~80年間傷を隠し続けた当事者の痛みに近づけるためにどういう本が良いのかを考えました。限定的に読まれるとしても本当に大切な本として作りたい。しかし、それによって読む人も限られて、誰にも読まれないかもしれない。それでも、記録にならなかった人の記憶・存在そのものを書物として残したいという思いがあります。チェルノブイリの作業員の日常には、だれも興味がないかもしれない。けれどアートブックとすることで表現できる可能性が広がり、こういう存在がいるということを社会の中に記録として残す抗いを本は可能にします。記録の価値がいつ、どのように役に立つかは分からないけれど、その本があることを誰かは知っていて、その誰かに、それを必要とする読者がいつかたどり着く。それによってアーカイブや記録というものが長い時間軸の中で役に立っていくことがあるのかもしれないと思います。
3時間に及ぶ濃密なトークを通し、震災後の表現について、また、「災間」「分有」という考えを会場とともに考える濃密な時間となりました。
第2回は、ゲストに佐々木和子さん(震災・まちのアーカイブ会員、神戸大学人文学研究科学術研究員)をお迎えします。
#2 ディスカッション「記録を集め、受け渡す」
日時:9月28日(土)14:00~17:00
場所:ギャラリーC
ゲスト:佐々木和子(震災・まちのアーカイブ会員、神戸大学人文学研究科学術研究員)
聞き手;佐藤李青、高森順子、宮本匠(災間文化研究会)
―
災間スタディーズ:震災30年目の分有をさぐる
期間:2023年11月18日(土)~2025年3月30日(日)
● 阪神・淡路大震災から「30年目の手記」
募集期間:2024年1月17日(水)〜12月17日(火)
● 分有資料室
期間:2024年3月30日(土)~2025年3月30日(日)※月曜休(祝日の場合は翌日休館)